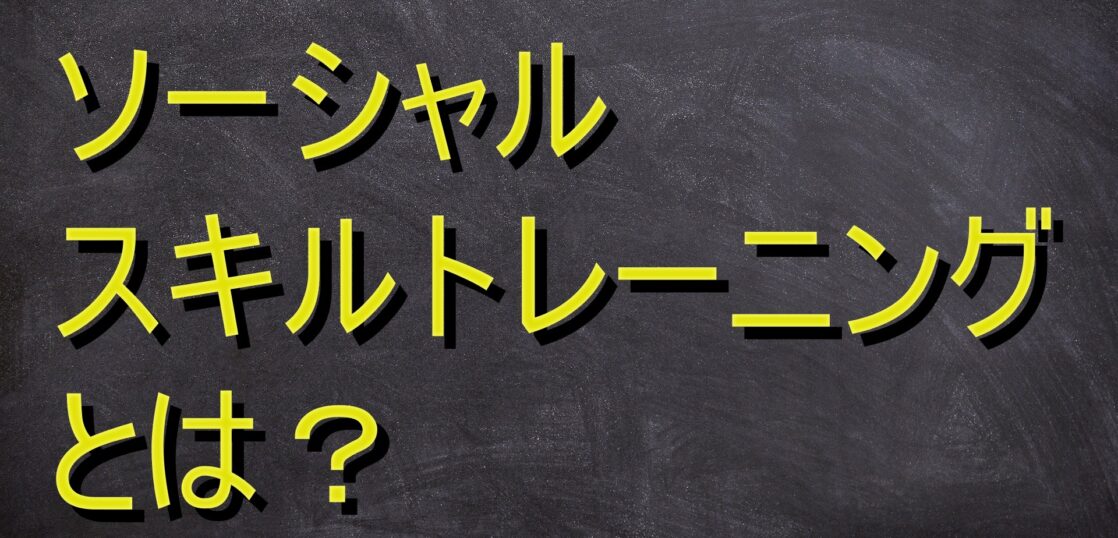皆さんこんにちは!本日も知って役立つ情報をみなさんと共有していきます!今回のキーワードは「発達障害 ソーシャルスキルトレーニング」についてです。
発達障害の治療のひとつとしてソーシャルスキルトレーニング(SST)というものがあるのはご存じでしょうか?
ソーシャルスキルトレーニングとは集団生活の中で上手くやっていくためのトレーニングの総称ですが、発達障害児のソーシャルスキルトレーニングは非常に重要だと考えられています。
そんなソーシャルスキルトレーニングについて解説していきます。
目次
ソーシャルスキルとは?

ソーシャルスキルとは集団生活や対人関係の中で上手くやっていくためのスキルです
ソーシャルスキルトレーニングの必要性

発達障害児は普通の子供と比べてソーシャルスキルを身に着けづらい傾向にあります。
なぜならば、それは以下の傾向があるからです
- ちぐはぐな認知発達
- 人への興味や関心が薄い
- 相手の気持ちを配慮する困難さ
- 習得したスキルをほかの場面で応用することの困難さ
以上の理由から発達障害児はソーシャルスキルを習得するのが難しいためソーシャルスキルトレーニングが必要と考えられています
発達障害児の社会性はこちらの記事に詳しく書いてます。良ければ合わせてご覧ください。
ソーシャルスキルトレーニングの進め方
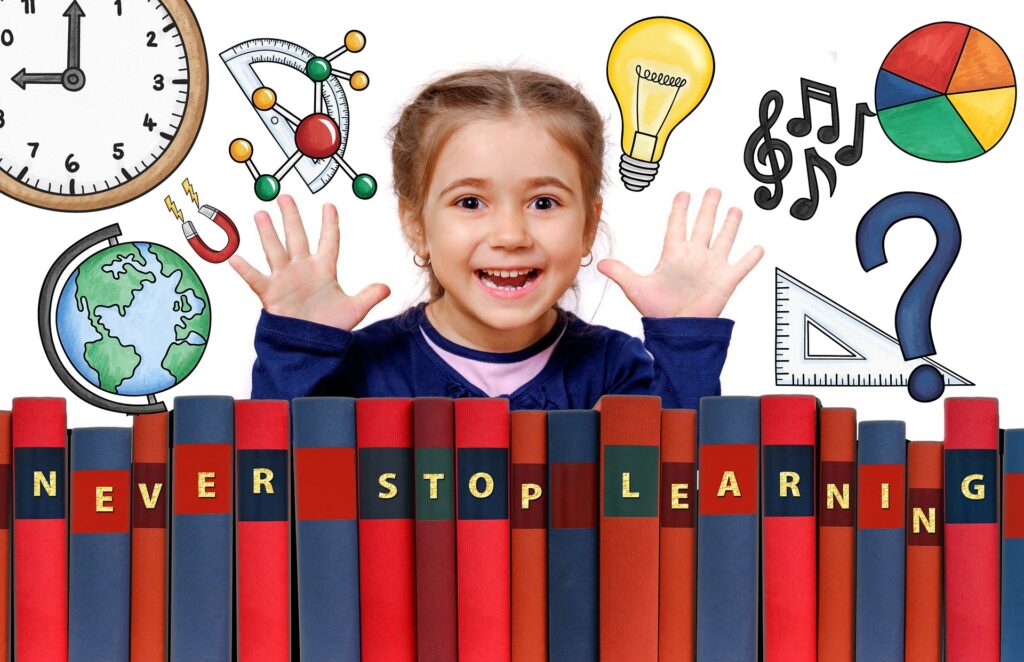
では実際にソーシャルスキルトレーニングの進め方について解説していきます
優先順位をつけてソーシャルスキルを身に着けていく
今一番習得してほしいソーシャルスキルに絞って習得していくというのが最も効果的なやり方です。
先ほど述べた通り発達障害には社会生活上色んな障害が見受けられます。またマルチタスクが苦手という特徴もあります
それらすべてを直したい。一気に習得してほしいというのが親心かもしれませんが、一気に習得となるとあれもこれも気を付けなければならないといった混乱状態を招いてしまうため、
ひとつひとつ必要なことから順番に身に着けていくというのがいいみたいです。
発達障害児はマルチタスクが苦手について深堀した記事はこちらの記事に詳しく書いています。良ければ一緒にご覧ください
大きすぎない目標が大切
例えばまずは挨拶からなど、いきなり大きなことからではなく小さなことから積み重ねていくことが大切といわれています
なぜなら、ソーシャルスキルトレーニングには極論ゴールはありません。
そのためお子さんも親御さんも一歩一歩達成感が味わえるように小さなことから達成していくのがいいとされています。
それにいきなり大きいことからやろうとして挫折してしまえば元も子もありませんしね。
トレーニングの時間を作る
ソーシャルスキルは日々の生活の中で活用されるものです。なので日常での場面場面での立ち回りが大切になります。
しかし、その場面の頻度が少ない場合もあります。そんなときは場面を意図的に作り出し、その中でソーシャルスキルを磨いていくことが重要となります。
まとめ
本日は発達障害のソーシャルスキルトレーニングについてお話ししました
- 身に着けたいスキルの優先順位をつける
- 小さな達成が大切
- トレーニングの時間を作る
ソーシャルスキルを身に着けて是非より良い社会生活を送れるようになりましょう。