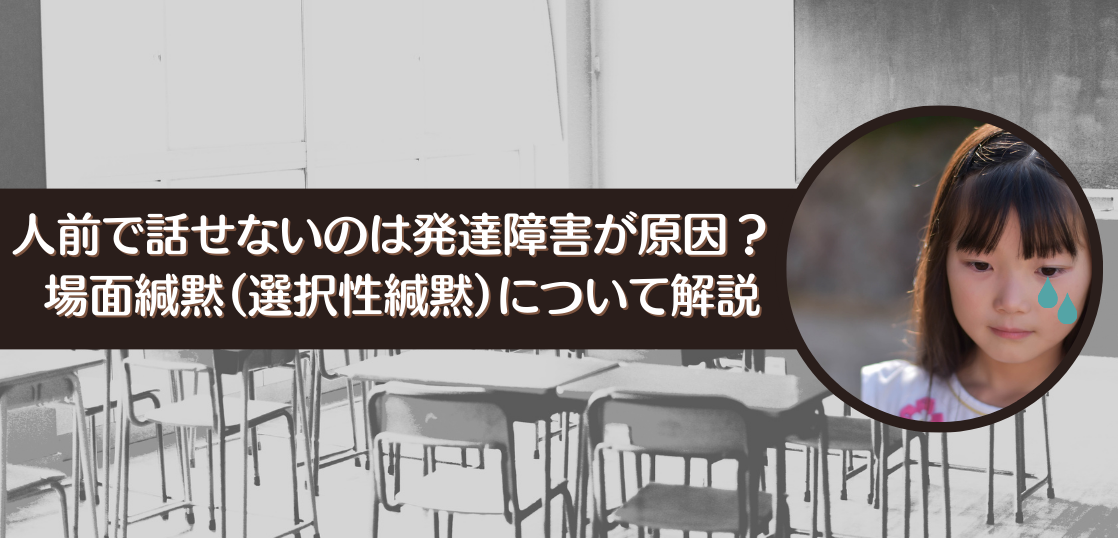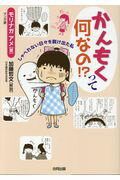こんにちは!こんばんは!今回も知っておきたい発達障害に関するノウハウや情報を提供させていただきます!
本日は「人前で話せないと発達障害」についてです。
「人前に出ることは得意!」という人よりは「人前は緊張してしまうから苦手」という人の方が多いのではないでしょうか。
人前で緊張したり、不安を感じることはごく自然な事なのです。
しかし世の中には言葉がどもってしまい話せず、赤面や発汗といった過剰な反応が表れる人もいます。
そこで今回は、何が原因で「話せない」という事が起きるのかを解説します。
目次
人前で話せない障害【場面緘黙】と発達障害の関係

家や慣れ親しんだ場所では流暢に話せるのに、学校や会社などの特定の場所では話せなくなってしまうという障害を場面緘黙(ばめんかんもく)といいます。
場面緘黙(ばめんかんもく)は選択性緘黙(せんたくせいかんもく)と呼ばれる場合もあります。
人見知りは数日程度でその状況に慣れて、徐々に話せるようになり改善されていきますよね。
しかし場面緘黙は慣れるという事がなく、一ヶ月以上話すことや大きな声を出すことができません。
発達障害と場面緘黙は区別がつきにくい
場面緘黙の場合、コミュニケーションに不都合が生じてくるため「発達障害ではないか?」と疑う方がいるかもしれません。
ですが発達障害と場面緘黙は別々の障害であり、発達障害があるからといって必ず場面緘黙とは言い切れないのです。
そうはいっても、発達障害があると対人関係やコミュニケーションをとることが苦手な場合が多く、上手く話せない・失敗したらどうしようと不安になり、周りの視線を過剰に気にする子が多いのも事実。
以上のことから言葉が上手く出てこない・話せない場合があり、発達障害と場面緘黙を併発している可能性があります。
・特定の場所で話さない以外は会話は流暢である
・言語能力の低下は普通はみられない
・生まれつき脳の発達が健常者と違っており対人関係やコミュニケーション能力に困難が生じる(自閉症スペクトラム障害/ASD)
・知的発達は問題がないが、読んだり書いたりの特定の事が難しい事がある(学習障害/LD)
発達障害の種類・特徴について詳しく説明している記事があるのでこちらも是非ご覧ください。
場面緘黙(選択性緘黙)について
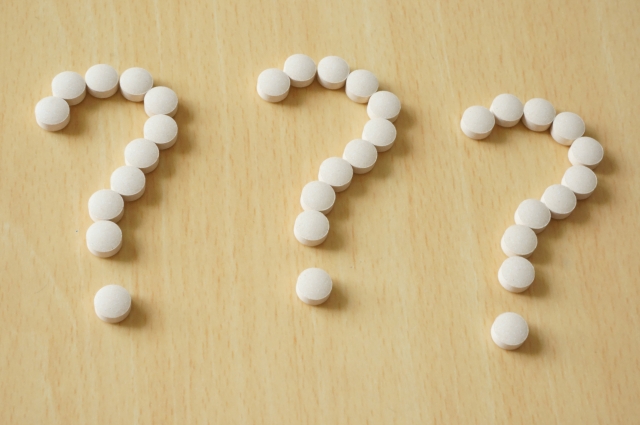
緘黙とは言語能力には問題がないにも関わらず、話せなくなってしまう症状です。
場面緘黙(正式な診断名は選択性緘黙)は、リラックスできる家などでは何の問題もなく普通に話せるのに、保育園や幼稚園、学校のような特定の場所では話せなくなる症状が続きます。
家族や親しい友人の前では話せても知らない人や心を開いていない人の前では極端に声が小さくなる・話せません。
一説には、不安から自分を守ろうとして起こる症状といわれています。
以下は場面緘黙(正式な診断名は選択性緘黙)について分かりやすく解説をしている動画です。
原因は特定されていない
場面緘黙(選択性緘黙)の詳しい原因はまだ研究段階であり、はっきりと解明されていません。
しかし不安・恐怖症の一種であり、本人が元々もっている不安になりやすい気質が関係しているといわれています。
不安になりやすい気質などの要因に加え「話しているのを人に聞かれる」「見られることが怖い」という心理的要因が合わさり、人前で話せなくなってしまうのです。
生まれつき「抑制的な気質」を持っている子供は慣れない環境では、とくに不安を感じやすくなります。
親のせいなのか
場面緘黙(選択性緘黙)の原因は家庭環境や親のせいではありません。
以前は虐待やトラウマによって場面緘黙になるともいわれていましたが、そういった根拠は証明されていないからです。
発症しやすい年齢・性別
一般的には5歳前後で発症することが多く、男女で比べると男児よりも女児の方がやや多いといわれています。
保育園や幼稚園の入園や小学校への入学時期や転校などの環境の変化があると発症しやすく、新しいクラスや集団に適応できない事もあります。
主な症状/見分け方
- 家や家族の前などのリラックスできる場面では流暢に話す
- 言語能力に問題はないのに特定の場所では話せなくなる
- 自己主張はせず、集団の中に入ると目立たないようにおとなしい
- 周りが話させようとすると頑なに話さない
以上のような症状が少なくとも一カ月以上続く場合は注意が必要です。
場面緘動(ばめんかんどう)とは
特定の場所で話せないのが場面緘黙(ばめんかんもく)です。
そして話せないのと同様に体が動かなくなってしまう・固まってしまうことを場面緘動(ばめんかんどう)といいます。
思うように体を動かせなくなるのですが、緘黙(かんもく)と同時に症状が出ることがあります。
緘黙(かんもく)の苦悩は理解されにくい

日本では場面緘黙(ばめんかんもく)があまり認知されておらず、早期発見や支援が遅れてしまうことがあります。
早期発見・支援が遅れるため、周囲の人に理解してもらえずに辛い思いをしている人が沢山いるのです。
緘黙は「話さない」のではなく「話せない」症状。
話せない理由は自分自身も分からないのに、周囲の人から「なぜ話さないの?なぜ黙るの?」と何度も聞かれることにストレスを感じながら過ごしています。
頑張って声を出しても「声が小さい」と言われたり、「友達の前ではわざと話さないなんて、ワガママだ!」と言われることもあるのです。
よって、本人は話したくても話せない・声が出ないんだということを理解し、強制的に話させようとするのは避けましょう。
早期発見の重要性
場面緘黙のある子どもの特徴は、園や学校では問題を起こさない・大人しくて目立たない点といえます。
目立たないため、障害が見過ごされ早期発見が遅れてしまうのです。
また医者からも「大人になったら治る」と判断され、親や周りの人も「いつかは治るだろう」と簡単に考えてしまい、様子をみようと放置してしまう可能性があります。
ですが自然と完治するケースは稀です。
場面緘黙を様子見のまま放置すると、鬱や不安症状、不登校などの二次問題を引き起こすことも少なくありません。
どこに相談すればいいのか
子供に場面緘黙の症状がみられたら早めの相談・受診をお勧めします。
病院を受診する場合は、お近くの精神科や心療内科を受診してください。
いきなり通院は不安という方は、おすまいの保健センター・子育て支援センター・児童相談所・精神保健福祉センターに相談してみましょう。
治療法は2パターンを考慮する

場面緘黙の治療法は主に二種類あります。「心理行動療法」と「薬物療法」です。
本人の不安が少ない場面から少しずつステップアップしていく方法。
個人のペースに合わせて少しずつレベルを上げていく。
不安を極力減らしながら会話・動作・集団行動などの出来ることを増やしていく。
本人の持つ不安症の改善のために薬剤を使用して不安を解消する。
完治させるために大切な事
緊張と不安を取り除く
「話せるようになる」ということは大事ですし、最終目標ですよね。
しかし「本人は話そうと思っていても話せない」ことをしっかりと受け止め、周囲の方は本人の緊張と不安を取り除く必要があります。
周囲の環境と協力
治療は長ければ数年にわたるため、本人だけではなく保護者も治療に参加する必要があります。
また周囲の環境も大切です。保育士や学校の先生にも治療方針を説明し、可能な限り協力を要請してください。
間違っても、園や学校で無理やり話させようとしてはいけません。これでは逆効果になってしまいます。
できることの代替えを考えよう
話さないことを決して責めないでください。
本人ができることで意思疎通を図るようにしてください。
筆談で会話をする、出欠をとる時には返事をするのではなく手をあげる、本読みをする時はみんなで一緒に読むなどであれば可能なお子さんも見受けられます。
場面緘黙に関するおすすめ書籍
【内容情報】(「BOOK」データベースより)
なんでクラスメイトと話せないんだろう?中学生になっても克服できないなんて…私ってダメなやつ!周りの人たちも自分も、「人見知りの激しい、とても大人しい子」だと思っていました。でも、ほんとは…場面緘黙症だったんです。
Rakutenブックス かんもくって 何なの!? しゃべれない日々を脱け出た私
- 子供の頃に場面緘黙症になった作者が自身の幼稚園時代からの出来事を振り返る!
- 自分自身のこと、家族や力になってくれた人のことを分かりやすく描いてコミックエッセイ化!
- 緘黙症がどういうものか、これを読めば分かる!
参考価格:¥1,408-(税込) 【楽天市場】2023年7月現在
ISBNコード:9784772613132
総ページ数:216P
【内容情報】(出版社より)
しゃべれないことの背景には不安が隠れています。
放っておかず、状況と本人の意志を把握してサポートにつなげましょう。
Rakutenブックスイラストでわかる子どもの場面緘黙サポートガイド アセスメントと早期対応のための50の指針
- 場面緘黙になった子供の症例や背景を掲載
- サポート時の「すべきこと」と「してはいけないこと」を解説!
- 周囲の環境の整え方や友達とのかかわり方のポイントを分かりやすくまとめたイラスト満載の一冊!
参考価格:¥2,640-(税込) 【楽天市場】2023年7月現在
ISBNコード:9784772613743
総ページ数:160P
まとめ
緘黙は日本ではまだあまり知られていない障害のひとつです。
それ故、周囲の人も正しい接し方を知らず、本人に辛い思いをさせてしまっています。
「話せ」と無理に強要したり焦らせたりするのではなく、話したくても話せないことを理解してあげてください。
周囲のサポートによって、障害の原因である「不安や恐怖心」を軽減することができます。
そして、早期発見・適切な治療受けられる環境になることを願っています。
最後まで読んで頂きありがとうございました。