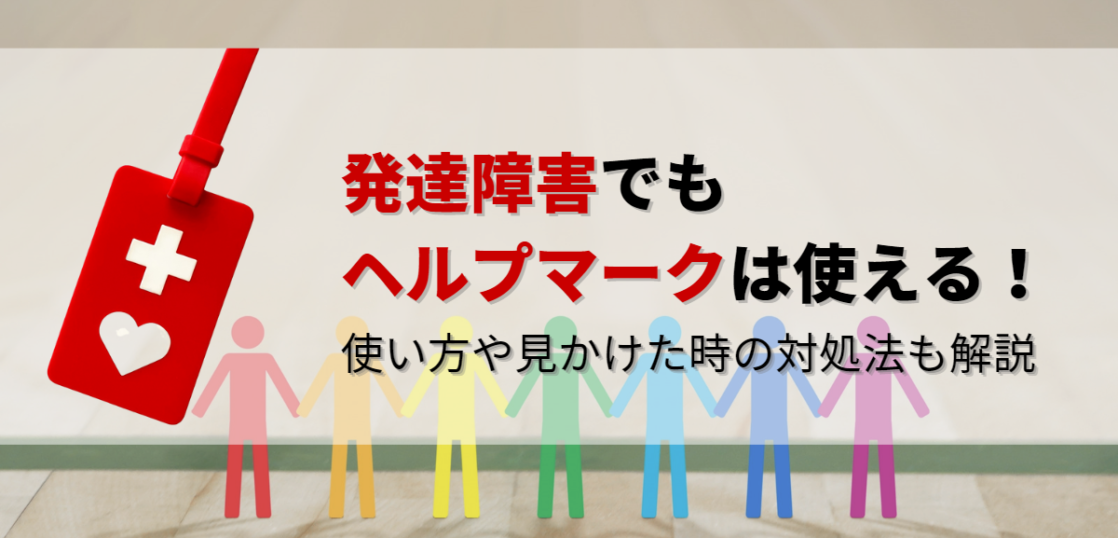こんにちは!今回も知っておきたい発達障害に関するノウハウや情報を提供させていただきます。
本日は「ヘルプマークは発達障害も対象」についてです。
発達障害は目に見えにくい障害。
公共機関で発達障害の症状が出てしまった場合、第三者に助けを求めるのは簡単ではありません。
ですがご安心ください。発達障害の症状を伝える有効手段の一つに「ヘルプマーク」があります。
今回は「ヘルプマーク」の使用方法や入手方法、ヘルプマークの現状を解説しますので参考にしてください。
目次
発達障害でも使えるヘルプマーク
ヘルプマークとは、外見からはわかりにくいけれど、障害や疾患などがあるために援助や配慮を必要としている人が周囲に知らせるためのマークです。
取り組みは東京都から始まり、全国へと普及し、令和3年10月現在では1都1道2府43県が導入しています。
対象者
配慮が必要な人たちが援助を受けやすくなるように作成されたマークなので、ヘルプマークの配布に特別な基準はありません。
ただ一般的に内部疾患や難病、精神疾患等、外側からは見えにくいが支援や配慮が必要な方が対象とされています。
よって、手助けや配慮が必要な人であればだれでも使用できます。
入手方法
お住いの自治体の行政窓口にて受け取れます。
東京都福祉保健局のホームページには各自治体の配布の有無や配布場所の一覧表が掲載しているので、お住いの地域の状況を確認してみてください。
参考元:東京都福祉保健局 /ヘルプマークについて /全国の普及状況
配布場所まで行くことが難しい場合、東京都在住であれば郵送対応(郵送料は各自負担)もしてもらえます。
お急ぎであればご自身で印刷し、身に着けることも可能です。
自作する場合は東京都福祉保健局のホームページからツールをダウンロードしてご使用ください。
参考元:東京都福祉保健局 /ヘルプマークについて /ツールダウンロード
ヘルプマークの使い方
ヘルプマークにはストラップが付いているので、リュックやカバンなど、人から見えやすい部分に身につけるといいでしょう。
ヘルプマークに同封されているのは説明書・記入用シールです。
記入用シールに支援内容・通院先など記入してヘルプマークの片面に貼っておけば、会話ができなくても支援のとっかかりになるかもしれません。
以下はヘルプマークの記入例です。
【記入例】
- 私は発達障害です。
- 大勢の人の中が少し苦手です。フラフラしていたり、パニックになっていたら静かな場所に誘導してください。
- 吃音(どもり)があるため、言葉が聞き取りにくいかもしれません。ゆっくり聞いていただけると助かります。
- 緊急連絡先 000-0000-0000 (母:●●宛)
ヘルプマークの現状

入手方法や自作ができることはわかりましたが、それでも実際に使用するとなると「メリットはあるの?」「デメリットはないの?」と気になりますよね…。
実際にヘルプマークを用いることで、「持っているだけで安心できる」「公共交通機関などで周囲の人に配慮してもらえた」というメリットがあるようです。
一方でまだまだ認知や理解が広まっておらず、ヘルプマークをつけていても周囲の人に意味が伝わらなかったり、心無い言葉を投げられてしまったりといったデメリットも見受けられました。
いざという時に支援を受けられるようにするには、ヘルプマークの使い方をマスターしておきましょう。
ヘルプマークは付け外しが可能ですから「普段はカバンの中にしまっておいて、援助や理解が必要な時に出す」ように、状況に合わせて使い分ける方法もあります。
実際に使用している方の声
実際の例を紹介していきます。
発達障害で自分から助けて下さいと言えず、ヘルプカードに自分の特性を記入して持っていたら安心できます。< 10歳/学生 >
引用:東京都福祉保健局 /ヘルプマークについて /ヘルプマーク・ヘルプカードエピソード集
上記のエピソードでは、ヘルプカードの良い面が紹介されています。
いざという時には「ヘルプカードを相手に見せる」という手段が取れますね。
援助を求める際のハードルが下がり、不安の軽減になるようです。
反面、認知度の低さにより、効果を実感できていない。という声もあるようです。
こちらのエピソードでは、ヘルプマークを持っていても周囲に伝わらなかったことが紹介されています。
もしかすると、周囲の人も「ヘルプマークには気付いているけど、どう援助すればいいのかわからない」のかもしれません。
少しずつ認知や理解が広まっていくように働きかけると共に「配慮が必要な時に助かること」をリストアップしておいたり、効果的な伝え方を考えてみるといいでしょう。
▼ ヘルプマークが「助け合い」のキッカケに。どんどん認知や理解が広まるといいですね!
現状では認知度が低い
マタニティーマーク等に比べるとまだまだ認知度が低いのがヘルプマークの課題になっています。
「障がい者総合研究所」による調査レポート(2017年データ)では、認知度の低さが示されています。
ヘルプマークの認知について質問したところ、47%がヘルプマークを「知っている」と回答しました。
地域別で比較すると、首都圏では「知っている」と回答した割合が55%と半数を超えたのに対し、その他の地域では38%に留まりました。
引用:障がい者総合研究所 /ヘルプマークの認知度・利用状況に関する調査


他にも、「利用時の周囲の反応が気になるから」「認知不足により役立たないと思うから」との理由で、マークの利用を敬遠している人が3割いることもこちらの調査からわかっています。
また「ヘルプマークが役立っていると思いますか」という質問には46%が「役立っている」と回答。
続けて「どのような場面で役立っていると考えますか」という質問には94%が「公共交通機関の利用時などに周囲から配慮してもらう」と回答しています。
そして同調査での「今後、ヘルプマークを利用したいと思いますか」という質問にも「利用したい」は49% 約半数という結果でした。
まだまだ認知度の低い「ヘルプマーク」。
中には「つけていたことで、心無い言葉を投げかけられ、心がくじけそうになった。」といったエピソードを聞くこともあります。
しかし調査データが示すように公共交通機関などで配慮を体感している、という人が半数近くいるということもまた事実です。
▼ こちらは、グッズを使うことで聴覚過敏の困りごとを軽減する方法を紹介した関連記事です!
ヘルプマークを見かけた時の対処法

ヘルプマーク利用者を見かけた場合どのように対応すればいいのでしょうか?ケースごとに確認していきましょう。
公共機関で見つけた場合
ヘルプマークを付けていて立っているのが辛そうであれば、落ち着いた声で「大丈夫ですか?」と尋ねるといいでしょう。
中には元気な方でもヘルプマークを付けながら席に座っている方もいます。
見た目が元気であっても見えない病気を抱えている場合もあるので、責め立てるような行為は慎んでください。
周囲に影響が出ている場合
落ち着きがない人や大声を出している人、人ごみに耐え切れず不安になりパニックになる人を見かけることがあるかもしれません。
ヘルプマークを付けていたら「何かお手伝いできることはありませんか?」と尋ねてみるといいでしょう。
もしかしたら支援を求めている可能性があります。
災害時に見かけた場合
健常者以上に冷静に対処するのが困難です。見かけた方は可能な範囲で力になってください。
例えば手をつないで一緒に逃げる、離れてしまった家族を探すなどです。
ヘルプマーク利用者の方は、災害時に即座に対応できるようヘルプマークに支援してほしいことをリストアップしておくといいでしょう。
まとめ
「助ける」というのは「相手の存在を理解し、認める」という前提の上で出てくる行動です。
日本には昔から「助け合いの精神」がありますが、昨今の社会での忙しさや慌ただしさから、そういったものが忘れかけられているのかもしれませんね。
そしてヘルプマークはそういった精神を思い出すきっかけを担っているのかもしれません。
ヘルプマークをつけていて困っている人をみかけたら、ヘルプマーク裏面を確認した上で対応してあげるとよいですね。
まだまだ普及途上のマークですが、この現状を知った上で、あなたなりの活用方法や普及協力方法を見つけてみてはいかがでしょうか。