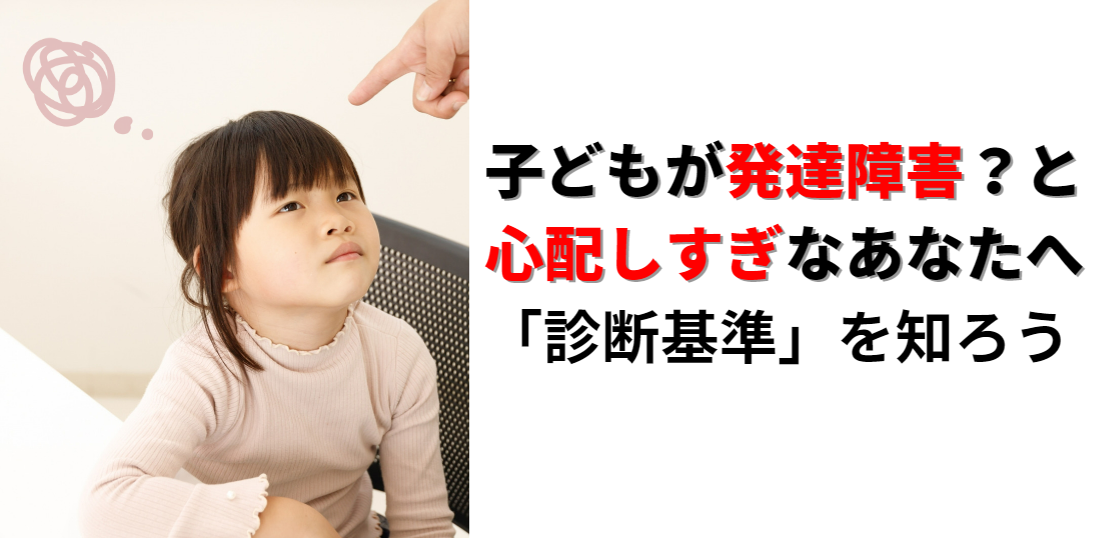こんにちは!こんばんは!今回も知っておきたい発達障害に関するノウハウや情報を提供させていただきます!本日は「発達障害心配しすぎ」についてです。
今回は「私の子どもは発達障害かも……」心配されている人のために、あるアンケート調査の結果や発達障害の診断基準などについて紹介しています。
目次
うちの子発達障害?心配しすぎ?アンケート結果から考察

「エデゥママアンケート」が2019年に全国の小中高生のお子さんがいる保護者300名に行ったインターネット調査があります。
調査では「お子さんの行動が発達障害かも、と心配になった」という問いに対して次のような結果でした。
- 「ある」:41%
- 「ない」:59%
「どんな行動を見て心配になったか」との問いにも、多い順にみると以下の通り、様々な回答が出揃っています。
- 一つのことに集中しすぎる
- 片付けることができない
- じっとしていられず、すぐにウロウロする
- 話がかみ合わない
- 友達と遊ばない
- 勉強に集中できずボーっとしている
- すぐにかんしゃくを起こす
- 書くのが遅い
最後に現在の状態について「成長とともに落ち着いたか」という質問をしたところ、次のような結果に。
- 「はい」:68%
- 「いいえ」:25%
- 「その他」:7%
引用:エデゥママアンケート調査
最後の問いからもわかるように、結果的に「心配しすぎ」だったケースが多いと読み取れますよね。反対に25%の方々は実際に診断を受けていることも読み取れます。
発達障害の診断基準を知る

発達障害と知るには医師からの診断が必要です。医師が診断する基準は一体どういったものなのでしょうか?
本項では発達障害の診断基準を解説します。
診断要素の一つに「社会的に困っているか?」がある
発達障害と診断される基準は何でしょうか?
発達障害の診断は、アメリカ精神医学会の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)に示されている基準に基づいて行われます。
「症状が社会的・学業的・職業的機能を損なわせている、またはその質を低下させているという明確な証拠」が含まれます。
「社会的コミュニケーションの障害」と「限定された興味」の2つとされています。
つまり「発達障害が疑われる様々な症状」があり、疑われるさまざまな症状によって「社会的にどのように困っているか?」という部分まで含め、はじめて診断が下されます。
先に紹介したアンケート調査の「どんな行動を見て心配になったか」との項目に出てきている答えはどうでしょうか?
よくよく見てみると「発達障害が疑われる症状」としてあげられる行動の一つが多数上がっていることに気づきませんか?
なかには「発達障害が疑われる症状」を複数持ち合わせている場合や、「発達障害が疑われる症状」のうちの一つがが突出している場合もあります。よって一概にすべてが「心配のしずぎ」とは言い切れません。
アンケート結果の7割が「その後、落ち着いた」と体感している結果からも、一つの症状を見て過剰に心配してしまっているケースが多いと推測されます。発達障害全般について解説している記事を別途用意しております。併せてご覧ください。
何歳から診断されるのか?
言葉の遅れやコミュニケーション障害が明らかな重度の自閉症スペクトラム(ASD)の場合は3歳までに診断されるようです。
しかし多くの場合は、子どもが保育園や幼稚園などの集団参加が始まったころに「社会的に困難さがあること」が認識され始め、その後の診断につながるといわれています。
また学習障害(LD)の場合は、小学校に上がり勉強が始まってから気づかれるパターンが多く見受けられます。
気になる方は通院されている小児科などで様子をうかがってみてはいかがでしょうか。
医師によって診断に差がある現状

しかしそれほど重度でないにもかかわらず、3歳未満の児童に診断が下りているケースもよく耳にします。
“M-CHATは確かに自閉症のハイリスク状態を検知することができます。陽性(リスクあり)とされた子どもの約半数が後に自閉症と確定診断されます。しかし、別の言い方をすれば約半数の子どもが自閉症にはならないのです。”“私が診た1歳台の2人の子どもは、多分過剰診断だったのですが、たとえM-CHATのようにその有用性が確立された方法で結果が陽性であったとしても、必ずしもすぐに療育に結びつける必要はないのです。”
引用:何か変だよ、日本の発達障害の医療(4) 判断が早すぎる!-CPN子どもは未来である
上記のように指摘している医師もいます。以上のように「一つの症状を取り立てて心配し相談すると診断名がついた」というケースもあるのです。
まとめ
今回は「発達障害と心配しすぎ」についてお話ししました。
あなたの気になっている事柄は「発達障害かもしれない症状」の一つですか?それとも「発達障害かもしれない症状」が複合され、社会的に(集団の中で)困っていますか?
上記の視点で見てみてもまだ不安や心配が取れないのであれば、まずは信頼できる周囲の人に相談するところからはじめてみましょう。
生活していく中でお子さんと向き合っているあなた自身の感覚を大切にし、自分の中に自然に入る情報や意見を大事にしてみてはいかがでしょうか?