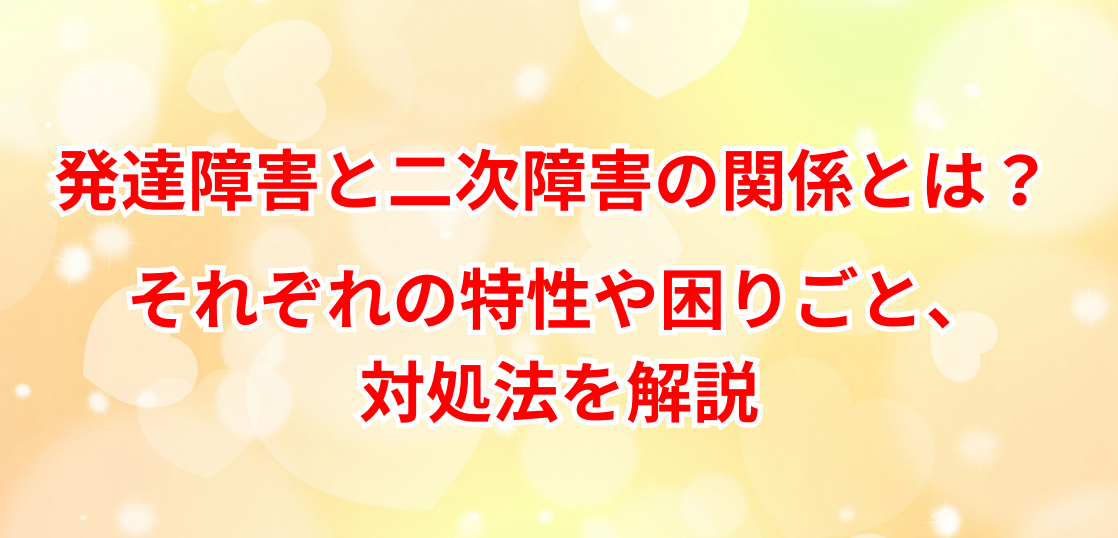こんにちは!こんばんは!今回も知っておきたい発達障害に関するノウハウや情報を提供させていただきます!
本日は「発達障害と二次障害」についてです。
発達障害とは生まれつき脳機能に偏りが見えられ、得意不得意の差が激しい障害をいいます。
発達障害の症状を放置していると二次障害に発展する可能性があるため、なんとしても食い止めなければなりません。
今回は発達障害の特性と二次障害について学び、ご自身のお子さんや身近な人にぜひ役立てていただければと思います。
目次
発達障害による二次障害

発達障害を特性別に分けると大きく3つに分かれ、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などが挙げられます。
先天的な脳機能障害のため詳細な原因は分かっておらず、根本的な治療にまで至りません。
発達障害の特性は合併する可能性があるため、特性を上手にコントロールできないと周囲とのコミュニケーションがうまく取れなかったり、集団行動ができないといった状況に陥ります。
「他人ができるのに自分ができない」といった苦しさや生きづらさにより大きなストレスを抱え、さらに周囲の人とコミュニケーションが取れず問題が生じてしまうのです。
以上のように必要な時にサポートを得られない環境、自分には向いていない環境にいることによって、やがて精神疾患を合併する可能性が出てきます・
精神疾患が現れるとより社会的生活を続けるのが難しくなり問題行動を起こしてしまいます。
上記の状態を発達障害における二次障害と位置付けています。
二次障害が起きる原因

発達障害を抱える人が必要なサポートを受けられず、周囲から十分な理解を得られない場合に二次障害へ発展すると言われています。
発達障害の特性が出る場面において、例えば道具や人的補助を利用して不得意な部分を補えば、問題が解決するかもしれません。
しかし周囲が発達障害へ理解をしていないと「だからあなたはダメなんだ」と指摘してしまい、発達障害者本人の自己肯定感が低下してしまいます。
次第に周囲から孤立化し、助けを得られない状態が続くことでストレスに苛まれてしまうのです。
二次障害の種類

発達障害の二次障害は「内在化障害」と「外材化障害」の大きく2つに分けられます。
内在化障害
発達障害の特性や自分自身に対して失望したり怒ることで自分の中に現れる症状をいいます。
具体的には以下の症状が見られるようです。
- うつ病
- 適応障害
- 不安障害
- 依存症
- 不登校、ひきこもり
- 自己肯定感の低下など
外材化障害
発達障害の特性や自分自身に対して失望したり怒ることで他者に現れる症状をいいます。
- 行動障害
- 暴力、暴言
- イライラ
- 感情不安定、自傷
- 非行など反社会的な行動
- 他者に対する攻撃、敵意など
自閉スペクトラム症(ASD)

最近よく耳にする「自閉スペクトラム症(ASD)」ですが、どのような特性があるのでしょうか。
イギリスの精神科医であるローナ・ウィングは、自閉スペクトラム症を3つの特性であらわしました。ウィングの3つ組と呼ばれるものです。順番に解説します。
社会性の問題
私たちは物心がついたときから、集団(学校、職場、習い事など)で生活します。自閉スペクトラム症(ASD)を持っていると、対人関係に支障をきたすことが多いとされます。
コミュニケーション能力の問題
相手に合わせてコミュニケーションを取るのが難しいです。話がかみ合わない、うまく話せない、冗談が通じないなど。
想像力の問題
物事を想像することが難しいです。相手の意図を見抜いたり、相手の気持ちを考えたりするのが苦手とされます。また想定外のことが起きると、冷静な判断ができず、混乱してしまうことが多いです。
ウィングの3つ組以外の特性
自閉スペクトラム症(ASD)には、ウィングの3つ組「社会性、コミュニケーション、想像力」以外の特性もいくつかあります。
こだわりが強い、運動が苦手、興味の幅が狭い、臨機応変な対応が苦手、集中しすぎてしまう(過集中)など。
上記特性を感覚過敏といいます。偏食がひどい、音に敏感、触られるのが苦手という症状があらわれることも多いです。
「視覚」「聴覚」「味覚」「嗅覚」「触覚」などの、諸感覚がとても敏感になっている状態を「感覚過敏」といいます。
感覚過敏研究所
たとえば、視覚がとても敏感であるときは「視覚過敏」、聴覚がとても敏感であるときは「聴覚過敏」という名前がついています。五感の他にも、平衡感覚の過敏や、温度感覚の過敏もあります。
人によって差がある
これらの特性(症状)は人によって差があるため、同じ自閉スペクトラム症(ASD)でも全然違うようにみえることもあります。
自閉スペクトラム症(ASD)があるからといって、必ずしもコミュニケーション能力が劣っているわけではありません。コミュニケーションに問題はないという方もいます。
また、運動は苦手で家に引きこもってしまうイメージが強いかもしれませんが、スポーツが好きで得意な自閉スペクトラム症(ASD)もいるのです。
そのように、自閉スペクトラム症(ASD)は、見た目はふつうで、症状も人によって差がありますが、生きづらさを感じることは共通して多いといえます。
自閉スペクトラム症(ASD)について詳しく知りたい方は、下記の動画を参考にしてください。
自閉スペクトラム症についての詳しい解説は以下の記事も併せてご覧ください。
自閉スペクトラム症(ASD)は治るのか?

自閉スペクトラム症(ASD)を治すことはできるのでしょうか。
2020年12月現在、自閉スペクトラム症(ASD)を治す薬はありません。治療法といえば、食事療法や療育、カウンセリングなどがあげられますが、必ずしも症状がよくなるとは限りません。
自閉スペクトラム症(ASD)は、生まれ持った障害です。そのため、定型発達の人が突然、自閉スペクトラム症(ASD)になることはありません。
注意欠陥・多動性障害(ADHD)

年相応の注意力に欠け、順序立てた行動が苦手であったり(注意欠陥)、落ち着きがなく待つのが苦手(多動性)などといった特性を持ちます。
注意欠陥が強く出る人もいれば、多動性が出やすい人もいます。注意欠陥と多動性が合わさった混合型もいるので、それぞれに適した対処法が必要です。
注意欠陥・多動性障害(ADHD)の一例
- 宿題を忘れる、持ち物を忘れる(注意欠陥)
- 落ち着きがなくじっとすることができない(多動性)
- 思いつきで行動したり、順番を待つことが苦手もしくはできないなど
学習障害(LD)
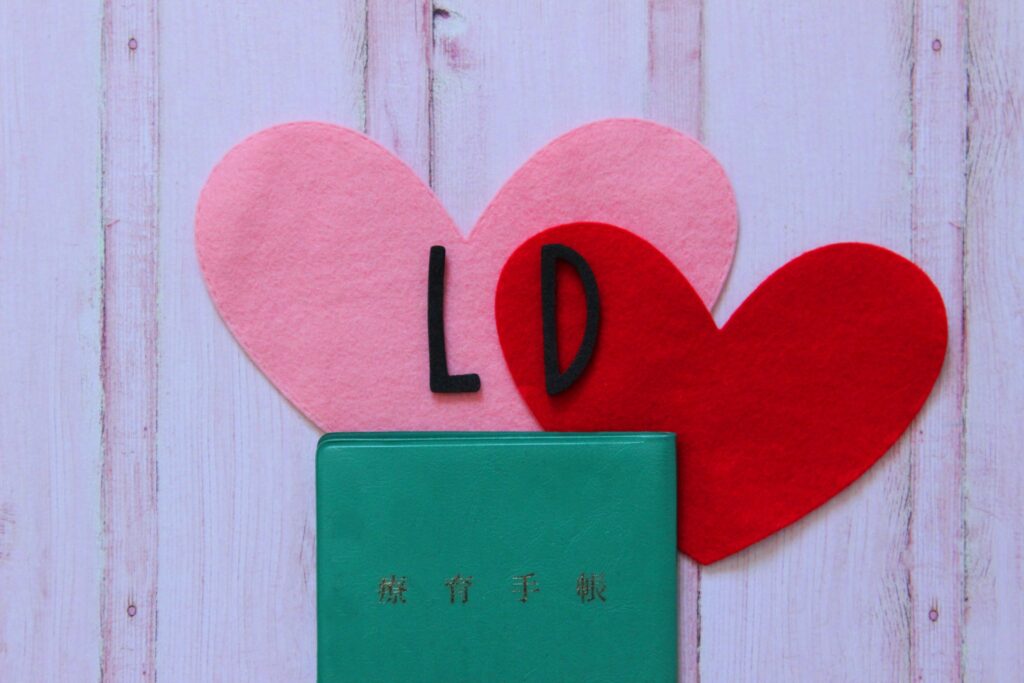
知的障害の遅れがないにもかかわらず聞く・話す・読む・書く・計算するなどの能力に困難が生じる発達障害の特性をいいます。
学習障害は読字障害、書字障害、算数障害3つに分類され、ツールなどを用いて環境を整える必要があります。
学習障害(LD)の一例
- 読字障害:単語を一つずつ文字を拾って読むなど特殊な読み方を行う
- 書字障害:文字は書けるが大きさがバラバラ、鏡文字になってしまう、文章が書けない
- 算数障害:計算ができない、+や-などの記号を取り扱えないなど
まとめ
今回は発達障害と二次障害についてお伝えしました。
発達障害における困りごとを放置しておくと、そのまま二次障害へ発展しやすくなります。
より過ごしやすい環境を整えることで二次障害を防ぎましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。